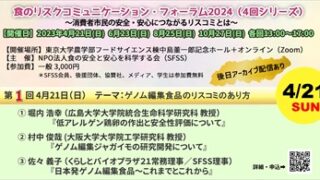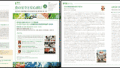関西大学 化学生命工学部 特任教授食品安全コンサルタント
広田鉄磨
日本の食品産業界のフードディフェンスは、かなり特殊な形に進化してしまったようです。録画カメラの設置がその対策の中心となり、それは2013~2014年にかけての農薬混入事件直後にピークとなった感がありました。いろいろな名称で呼ばれていますが、日本でのカメラは録画機能単独のものばかりであり、画面を誰かが常に見張っているといった即時対応能力はありません。
録画カメラの設置が警察にも歓迎されていることは、平成27年度版警察白書を読み解けば明らかです。団塊世代の熟練警察官の大量退職、若い警察官の「どぶ板」捜査不慣れなどで 背に腹は変えられない選択なのでしょう。AV機器メーカーにとっては、長く続いた電器不況からの回復へのささやかなカンフル剤程度の効果はあったでしょう。警備産業に関していえば、監視カメラの単純配備にとどまらずカメラ画像処理技術の高度化、ICタグなどとの組み合わせでリアルタイムで作業者の位置判定・アクセスコントロールが可能という売り込みの糸口にできました。そして冷静な分析が求められているはずのメディアに関して言えば、カメラの数で勝負という単純明快な記事を提供できることで 手放しで、歓迎されてしまったようです。記事を読む側にも「効果があろうがなかろうが企業としてなにかしら行動をとってほしい」という日本特有のアクションに対する期待感がありました。
しかしながらカメラで冷凍食品への農薬混入事件のような内部犯行、それも警備機器の盲点まで知り尽くした熟練工が、周到に準備して臨む毒物混入事件というものを抑止できるというのでしょうか。一例をあげると、コンビ二での録画カメラの配備は100%に近いところまでなっており商業施設としては最高水準を誇ります。しかし皮肉にも、窃盗事件は実は深夜のコンビ二で最も多く起きており、その検挙率も高いものではありません。
経済的に合理的な判断をする犯罪者であれば、利益と(逮捕・服役という)損失をはかりにかけるのでしょうが、上のコンビ二の例では深夜の店員がすくない状況が作り出す「ヒトによる抑止力の不足」が、カメラの威嚇をいとも簡単に打ち消してしまいます。農薬混入事件のように復讐を意図するものであって 「怨嗟」という もうひとつの強烈な、しかし非経済的な要因が入り込む場合には、経済学的な犯罪抑止理論、つまりカメラ=威嚇=犯罪の抑止力であるといった単純な図式は成り立ちにくくなります。
フードテロが世界中を見渡しても、過去40年間でアメリカ・オレゴン州で起きた一件のみであることは厳然たる事実です。かつ、日本という比較的安定した社会に対して、テロをしかけること自体成功率の低い所業です。テロよりはるかに起きやすいのは、個人的な怨嗟に基づく混入事件であって、このような犯罪の抑止には企業風土・労務管理の改善を中心とする対策しかありえません。
現在の日本のフードディフェンスの問題点の引き金となったのは、過去日本の食品産業が「自分で考える」という態度を放棄する方向に進んできたことに遠因があると思われます。マニュアル本のようなチェックリストに頼り切り 書いてある通りにしておけば誰も批判しないだろうというような単純な思考方式から抜け出し、HACCPに代表される客観的かつ批判的な判断方式に立ち返り、実際にはどんな事件が起きうるのか どんな対策を必要とするのか、真剣に自ら考え議論すべき時に至ったといってよいでしょう。

アメリカでも当初は 何でもかんでもテロの対象となりかねない といった まったくもって動転したとしかいえない論調が支配的であった時期がありました。調合タンクのような原材料の集中する箇所では 大規模汚染を引き起こすのが容易であるから そこには必ず防御を施さなければならない といったハード偏重路線です。しかし911事件より15年経過した現在では 食品産業をテロの対象とすることは あまり起き得ないのではないか という口調に変化しており対策も 右に示すような Employees FIRST(http://www.fda.gov/Food/FoodDefense/ToolsEducationalMaterials/ucm295997.htm 従業員がお互いに注意しあうことで 事件の発生を防ぐ。FDAはポスターを各国語で作製しています)という現実路線に回帰してきています。日本もまた 監視カメラ設置騒動という 初期の動揺を経験しましたが そろそろ冷静に現実に向き合うべきときにいたったといえるでしょう。