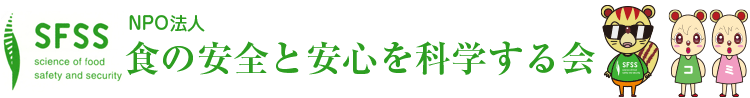立命館大学BKC社系研究機構客員研究員
畝山智香子
小林製薬が製造・販売した紅麹を含むいわゆる健康食品による健康被害が大きな問題となっています。原因は不明ですが、もともとこの手の製品は一般的な食品に比べてリスクが高く、何か問題があった場合には健康被害が発生する可能性の高いものです。ここでリスクが高くなる理由を簡単におさらいしておきます。
前提 食品は未知の化合物の塊
食品は安全であるべきですが、現実には食品はそれほど「安全が確認されているもの」ではありません。私たちが健康に良いと思って食べている野菜や果物の成分のすべてがわかっているわけではなく、中には明確に「大量に動物に投与すると有害である」物質も含まれます。そして同じ野菜でも含まれる化合物は相当違います。例えば青いトマトと赤いトマトは味も成分も違いますがどちらも「同じ」トマトとみなされます。食品とはそのようにわりと曖昧でよくわからないものなのですが、それを私たちが「安全に」食べられるのは、いろいろなものを食べているから、です。そのことを再確認したいと思います。
1.摂取量が多くなる
健康食品の場合、普通の食生活からはとることがないだろう量をとることになることがあります。紅麹の場合は、日常生活でたまに豆腐よう料理を食べる場合とサプリメントを毎日摂る場合とでは圧倒的にサプリメントのほうが紅麹成分を多くとることになります。
2.食経験がない
料理に使われた食材中の紅麹には食経験があると言えますが、紅麹を錠剤にしたものは食経験がありません。それを摂取することでどのような反応が生じるかはわかりません。健康被害が出る人は人口のごく一部だったり長期間の摂取後だったりするので、一般的に食経験とは20-25年以上にわたって、一国の全住民程度の数の人たちが食事の一部として食べてきた実績をいいます。それでも発がん性のような有害影響はわかりません。
3.効果があれば副作用がある
医薬品の場合、効果には必ず副作用が伴うことが多くの人に認識されていると思います。それは医薬品だから、ではなく、食品であってもそうです。一般的にいわゆる健康食品は効果がほとんど実感できないようなものが多いのですが、紅麹の場合実際に効果があったという人がいるようです。それは処方薬として使用されているロバスタチンと同じ成分を、処方量にかなり近い量含むためです。そのため海外ではサプリメント使用者に有害事象が報告されていて、ダイエタリーサプリメントの成分としては認められないと判断されたり細かい注意書きを求められたり医師の指導の下でのみ使うように助言されたりしています。もともと紅麹はリスクの高いもので、そのリスクの高さをどう管理するかについてレベルの高い安全性確保対策が必要なものでした。
4.健康でない人が使う可能性が高い
健康食品は病気の人が摂取することを想定していません。しかしコレステロールが下がる効果を宣伝しているため、コレステロールの高い人が摂取することになります。この場合コレステロールだけがやや高くて他は全く健康な人、というのはどうやって確認するのでしょうか?コレステロールが高い状態が長く続いている人は自分では気がつかないうちに心血管系や肝臓などに何らかの異常があるかもしれません。実際には明確に持病があって病院で薬をもらっていながら健康食品を使っている人が多いことが各種調査で報告されています。
5.専門家ではない消費者がリスク管理
医薬品の場合、効果がちゃんとでているかや副作用は医師が適切に管理します。定期的に血液検査をして異常があれば休薬したりほかの薬に変えたりします。食品の場合には自分で判断することになりますが、素人が検査もなしに何らかの障害の兆候をみつけるのは困難でしょう。
6.リスクの高さを多くの人が認識していない
いわゆる健康食品はリスクが高いということが一般の人たちに広く知られてはいません。例えば包丁はリスクが高いことはみんなが知っているので使い方に注意しますし、誰かが「包丁を振り回して遊ぶと楽しい」などと言ったりしたら周囲の人たちみんなが止めるでしょう。健康食品の場合には薬の代わりに健康食品を、と勧めるような人をみんなで止める状況にはなっていません。
以上、今回の事例からリスクが高くなる要因のいくつかを紹介しました。出版から少し時間が経ちましたが以下の本を改めてお勧めします。
「健康食品」のことがよくわかる本 日本評論社 2016年