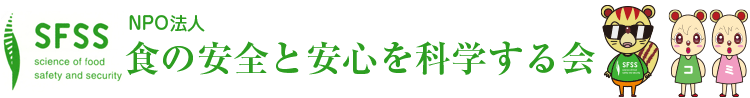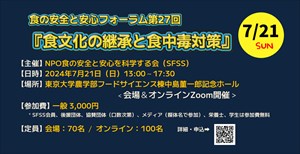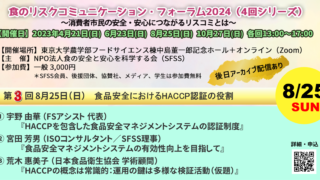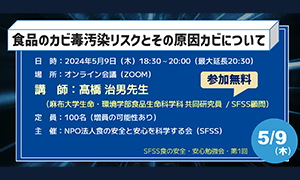食のリスクコミュニケーション・フォーラム2023
『消費者市民のリスクリテラシー向上につながるリスコミとは』
第4回テーマ:『健康食品のリスコミのあり方』(10/29)開催速報
【開催日程】2023年10月29日(日)13:00~17:00
【開催場所】東京大学農学部フードサイエンス棟中島董一郎記念ホール+オンライン会議(Zoom)ハイブリッド開催
【主 催】NPO法人食の安全と安心を科学する会(SFSS)
【後 援】消費者庁、東京大学大学院農学生命科学研究科
【賛助・協賛】キユーピー株式会社、旭松食品株式会社、カルビー株式会社、
株式会社セブンーイレブン・ジャパン、日清食品ホールディングス株式会社、
日本生活協同組合連合会、サラヤ株式会社、日本ハム株式会社、東海漬物株式会社
【参加費】3,000円/回、学生は1,000円/回
*SFSS会員、後援団体(先着1~2 名程度)、メディア関係者(取材の場合)は参加費無料
3人の専門家より、それぞれのテーマに沿ったご講演をいただいた後、パネルディスカッションでは参加者からのご質問に対して活発な意見交換がなされました。
【プログラム】
13:00~13:50『セルフケアに上手に使うためのヒントと注意点』
宗林 さおり(SFSS理事・岐阜医療科学大学教授)
13:50~14:40『健康食品をめぐる報道』
大村 美香(朝日新聞くらし報道部記者)
14:40~15:30『機能性表示食品のリスクとベネフィット』
山﨑 毅(SFSS理事長)
15:30~15:50 休憩
15:50~17:00 パネルディスカッション
『健康食品のリスコミのあり方』
パネリスト:上記講師3名、特別ゲスト 畑中三応子氏(食文化研究家)
進行:山崎 毅(SFSS理事長)

宗林さおり先生

大村美香先生

山﨑毅理事長


*講演要旨ならびに講演レジュメは以下のとおりです:
➀宗林 さおり(SFSS理事・岐阜医療科学大学教授)
『セルフケアに上手に使うためのヒントと注意点』
機能性成分についていくつかのポイントがある。まずは医薬品にも使用されており、機能性が極めて高いもの。これらについて同じ表記となっているが量的多少を見ること。一方食事に+オンする機能性成分は一体どの程度が適量なのかの議論も始めなくてはいけない。 逆に注意点として、保健機能食品でなくその他の健康食品でも食薬区分によって身体作用が極めて大きいものがあることも知らないといけないし、その製品であっても肝機能障害等体調を崩した際の比較的早い対応の必要性についても議論したい。
<宗林先生講演レジュメ>
➁大村 美香(朝日新聞くらし報道部記者)
『健康食品をめぐる報道』
医薬品などと異なり、食品には身体への効果や効能の表示はできないが、例外的に「保健機能食品」だけが、健康への働き(機能性)を表示してよいとされている。保健機能食品には、特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類がある。しかし、制度の認知度は必ずしも高くなく、これ以外の「いわゆる健康食品」も含め、各種の違いを明確に認識している人は少数だ。国民の半分が健康食品を利用しているとも言われる中、なぜこのような現状なのか。健康食品をめぐるこれまでの報道を見ながら、考えてみたい。
<大村先生講演レジュメ>
➂山﨑 毅(SFSS理事長)
『機能性表示食品のリスクとベネフィット』
機能性表示食品は、食品事業者自らが機能性/安全性の科学的根拠情報を消費者庁に届け出て開示
し、消費者市民がその公開された科学文献情報等をもとに、商品の合理的選択を行う国の制度だ。本年 6月、消費者庁は機能性の科学的根拠が薄弱として、一部の届出企業に対して行政指導を行ったが、消費者市民が試してみたいと思う機能性食品のベネフィットは、どの程度の科学的エビデンスなら許容されるのか。あくまで毎日摂取する食品である限り、医薬品のように有効性が強いからこそ副作用も許容せざるをえない世界はなじまない。「食品の機能性には寛容に、安全性には厳しく」を基本として、機能性表示食品のリスクとベネフィットのバランスの重要性について議論したい。
<山﨑理事長講演レジュメ>
④パネルディスカッション 特別ゲスト:畑中三応子氏(食文化研究家)
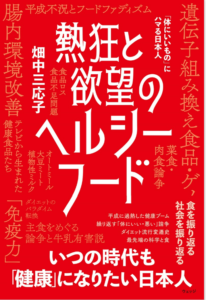
*なお、参加者アンケートの集計結果は後日掲載します。
(文責・写真:miruhana)